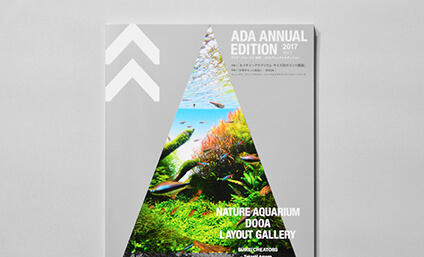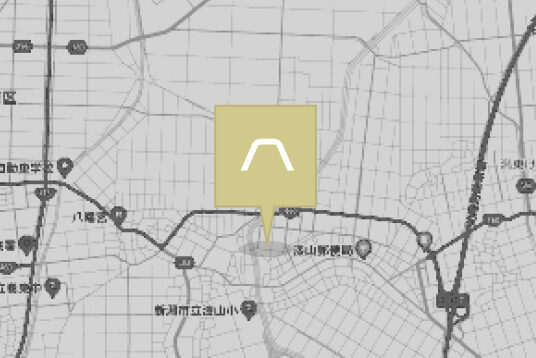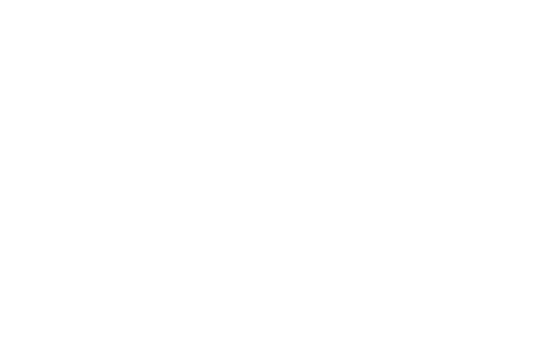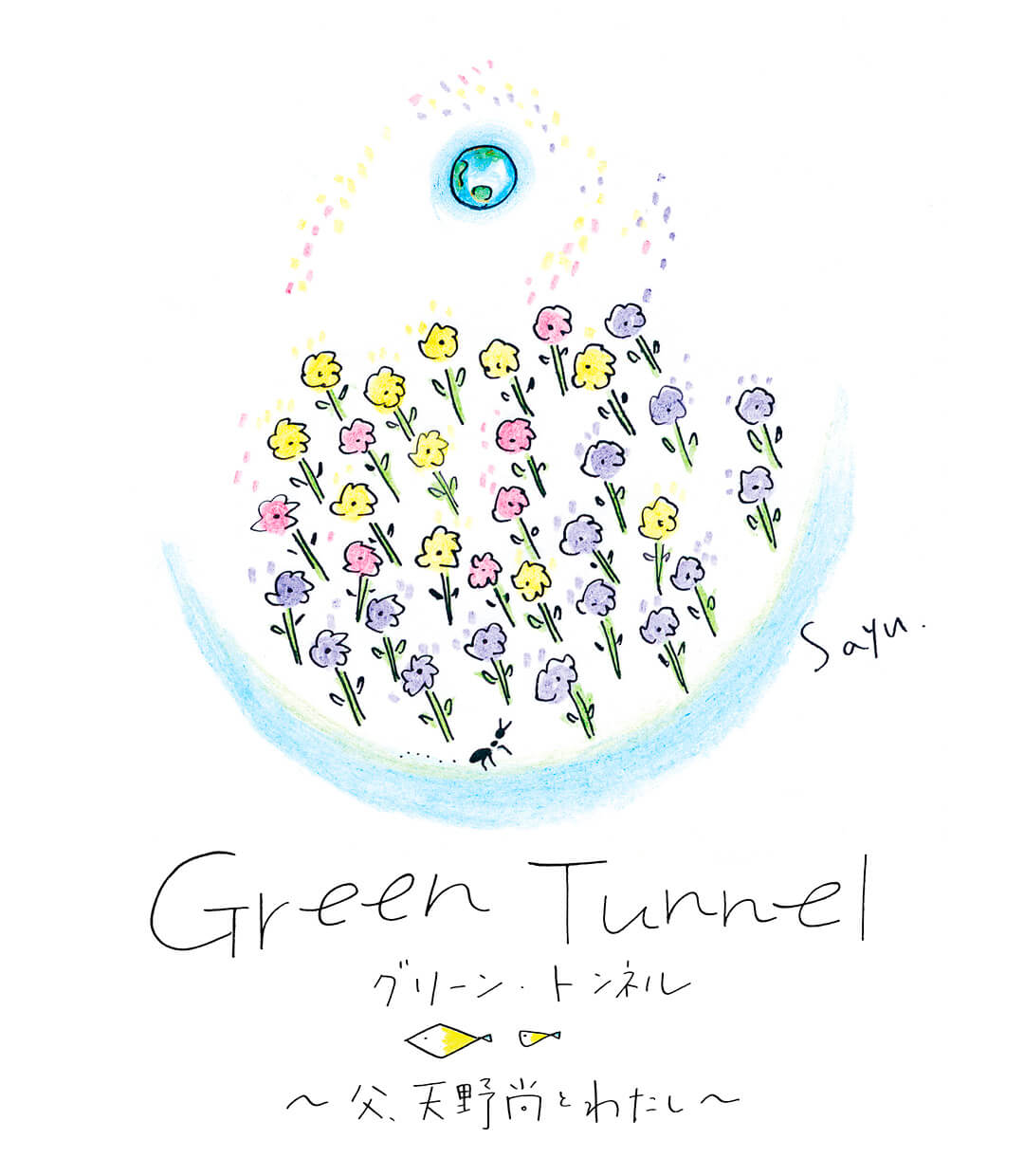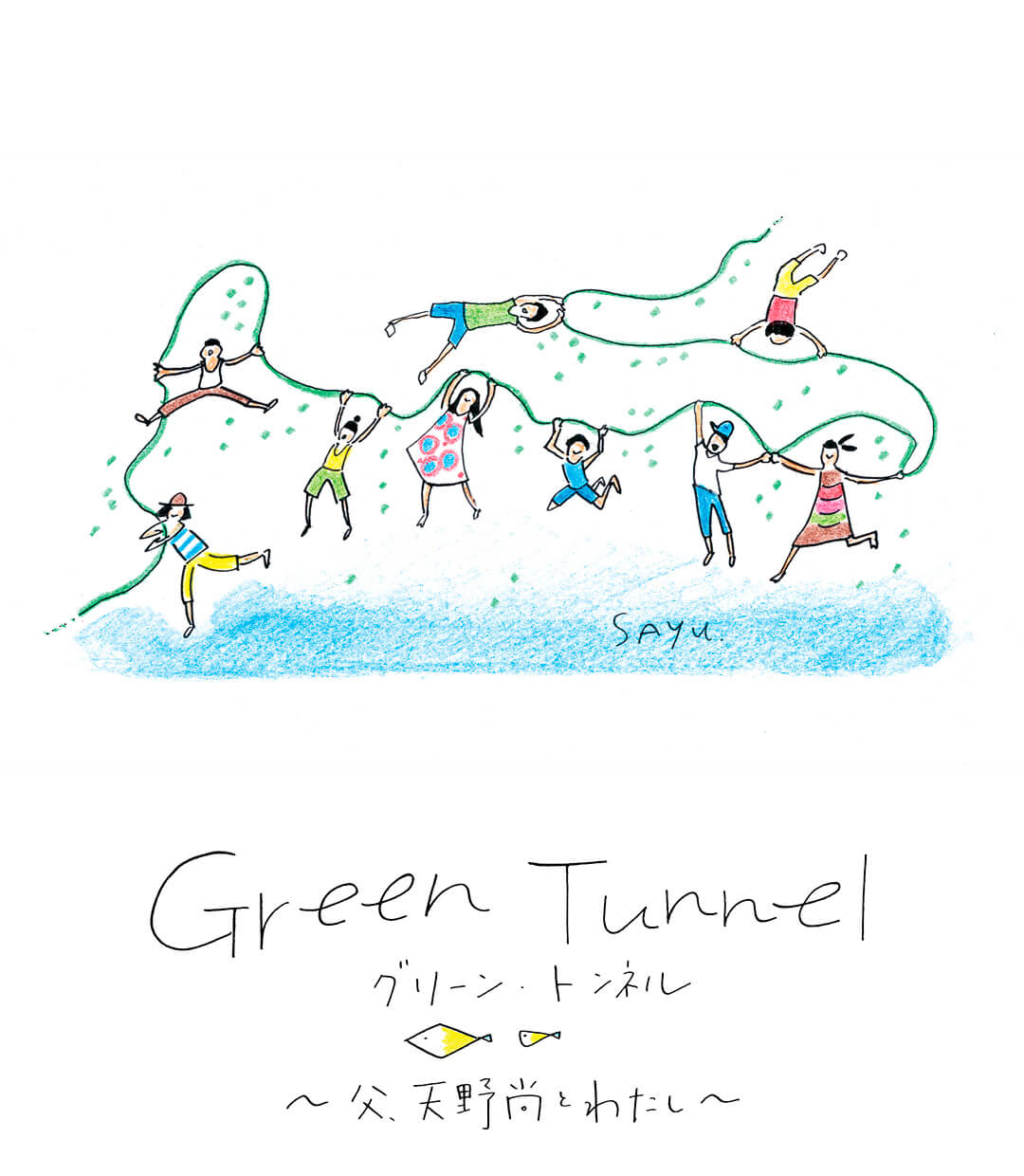グリーン・トンネル 〜父、天野 尚とわたし〜 #08「小さな祈り」
誰かのために、心から強く祈る。私の記憶がある限り、私にとって最初のその誰かは、父であった。
父がアマゾンへ行くという。当時8歳の私はアマゾンがどこにあるのかもよく分からない。「アマゾンは日本の裏側だよ」という父からの情報で「そうか、地球は丸いんだった」という、当たり前すぎる、けれどもつかめないでいたその事実に対する実感を得た。私は、一気に世界というものが広がった気がして、不思議の迷路に迷い込んだ蟻になった気分だった。たったひとつの小さなものから宇宙が始まる。幼いころは、宇宙の入り口が多い。私は、私の世界の裏側へ旅に出る父によって、初めてここが地球であることを感じた。「アマゾン」。そこはここから最も遠い場所、なぜなら地球は丸いから。そんな当たり前のことに妙に感動し、そしていろんな不思議が生まれる。宇宙には上も下もないのに、地球に上と下、表と裏があるのはなぜだろう。地球は丸くて回っているのに、私の目に映る地平線が真っ直ぐで、ちっとも目が回らないのはなぜだろう。小さな蟻はそんな不思議の迷路で迷子になっていた。アマゾンをキーワードにして始まった、なぞなぞ迷路。
私がそんなことをぐるぐると考えて毎日を過ごしている間、父と母は忙しなく旅の準備をしていた。8歳の私には、アマゾンに対する具体的なイメージがほとんどないために、母が気を揉む理由もあまりよく分からなかった。母は、アマゾンという、いわばまだ未開拓の危険な地へ父を送り出すことをそれなりに不安がっていた。私は心配というよりも、むしろ日本の裏側の世界という場所に父が行くことに対して、なんとなく好奇心が芽生えていた。
ある日、「どうして地球は丸くて回っているのに、そこで生きる人間は、目が回ることもなく、真っ直ぐな世界で、地球から宇宙にこぼれたりすることなしに生きていられるの」と私は母にたずねてみた。母の答えは「人間があまりに小さすぎるのよ」という簡単なものだった。私は今でもそれを強く覚えている。意外と私はその答えが腑に落ちたのだ。そして、どこかその答えに安心した。地球に、「お前のようなちっぽけなものに、私が分かるはずないでしょう」と言われた気がした。それはどこか、底なしの愛情のようなものに感じた。
父がアマゾンに旅立つ前日、ADAの本社では社員による壮行会が開かれた。沢山のメッセージが書かれたハチマキを持って帰って来た父を見て、やはりそれほどまでの気合いが必要な場所なんだ、と初めて父を送り出すことに少し不安を覚えた。そして、父はアマゾンへ旅立った。
父が旅立ってからほどなくして、母と妹と3人で長野県の戸隠神社を訪れた。母は何度か私たちを戸隠神社へ連れて来てくれたことがある。けれど、奥社へ立ち入ったのはそのときが初めてであった。当時はまだ補修前で、古い鳥居や社殿が独特の雰囲気を醸し出していた。大きな杉の神木が立ち並ぶ参道は、歩いていると心も身体も浄化されていくような気持ちのよいものであった。いつもは本殿まで行って引き返すのだが、その日は特別だった。「お父さんが無事に帰って来られるようにお祈りして行こう」と母が言い、私たちは奥社へお参りに行くことにし、長い石階段を上り始めた。いつもはぐずつく妹も、嫌になるほどの長い階段を、文句ひとつ言わずに上っていた。1時間ほどしてやっとたどり着いた小さく古い社殿は、ひっそりと佇んでいた。そこには、私たちの他にも何人かの参拝客がいて、大事そうに、どこかに通じるかのように、お参りしていた。私と母と妹も、父が無事に帰ってこられるように、心から、祈った。私は父が日本の裏側の世界に行っている間、その世界にいる父を、いつも家にいる父よりもずっと強く意識して生活していた。世界で一番遠い世界にいる父が、今ごろどうしているのか、いつも気になっていた。
駐車場に向かって歩いていると途中に清流があった。「わあ、きれい」と母がその清流の美しさに感動していた。私たち3人はその清流をしばらく眺めていた。自然の水草がきらきらしていて、まるで父の石組レイアウトを彷彿させるような、洗練された自然の美しさがそこにはあった。私たちの祈りに、父の何かがそっと呼応していたかのように。もしかしたら、それは母の想いに応えたものかもしれない。誰よりも母のために父に無事に帰って来てほしい、そう思ってしまうほど、私は心配性の母も気になっていたのだ。
数週間後、真っ黒に日焼けして、痩せこけた父が帰って来た。けれども、とても良い顔をしていた。話を聞くよりまずその姿が、父が何を見て、得てきたのかを物語っていた。父は沢山のお土産を私たちに持って帰って来てくれた。見たこともない色合いのタペストリーには動物や植物が手刺繍されていた。ミサンガやヘアバンド、バッグ、そこからは初めての匂いがした。世界の裏側からやって来たものたちを自分の部屋に持って行くと、所在なさそうに、他のものから浮いていた。その夜は、母が父の好きなものばかりをこしらえて、私たちは父の帰還をお祝いした。
父がアマゾンへ行くという。当時8歳の私はアマゾンがどこにあるのかもよく分からない。「アマゾンは日本の裏側だよ」という父からの情報で「そうか、地球は丸いんだった」という、当たり前すぎる、けれどもつかめないでいたその事実に対する実感を得た。私は、一気に世界というものが広がった気がして、不思議の迷路に迷い込んだ蟻になった気分だった。たったひとつの小さなものから宇宙が始まる。幼いころは、宇宙の入り口が多い。私は、私の世界の裏側へ旅に出る父によって、初めてここが地球であることを感じた。「アマゾン」。そこはここから最も遠い場所、なぜなら地球は丸いから。そんな当たり前のことに妙に感動し、そしていろんな不思議が生まれる。宇宙には上も下もないのに、地球に上と下、表と裏があるのはなぜだろう。地球は丸くて回っているのに、私の目に映る地平線が真っ直ぐで、ちっとも目が回らないのはなぜだろう。小さな蟻はそんな不思議の迷路で迷子になっていた。アマゾンをキーワードにして始まった、なぞなぞ迷路。
私がそんなことをぐるぐると考えて毎日を過ごしている間、父と母は忙しなく旅の準備をしていた。8歳の私には、アマゾンに対する具体的なイメージがほとんどないために、母が気を揉む理由もあまりよく分からなかった。母は、アマゾンという、いわばまだ未開拓の危険な地へ父を送り出すことをそれなりに不安がっていた。私は心配というよりも、むしろ日本の裏側の世界という場所に父が行くことに対して、なんとなく好奇心が芽生えていた。
ある日、「どうして地球は丸くて回っているのに、そこで生きる人間は、目が回ることもなく、真っ直ぐな世界で、地球から宇宙にこぼれたりすることなしに生きていられるの」と私は母にたずねてみた。母の答えは「人間があまりに小さすぎるのよ」という簡単なものだった。私は今でもそれを強く覚えている。意外と私はその答えが腑に落ちたのだ。そして、どこかその答えに安心した。地球に、「お前のようなちっぽけなものに、私が分かるはずないでしょう」と言われた気がした。それはどこか、底なしの愛情のようなものに感じた。
父がアマゾンに旅立つ前日、ADAの本社では社員による壮行会が開かれた。沢山のメッセージが書かれたハチマキを持って帰って来た父を見て、やはりそれほどまでの気合いが必要な場所なんだ、と初めて父を送り出すことに少し不安を覚えた。そして、父はアマゾンへ旅立った。
父が旅立ってからほどなくして、母と妹と3人で長野県の戸隠神社を訪れた。母は何度か私たちを戸隠神社へ連れて来てくれたことがある。けれど、奥社へ立ち入ったのはそのときが初めてであった。当時はまだ補修前で、古い鳥居や社殿が独特の雰囲気を醸し出していた。大きな杉の神木が立ち並ぶ参道は、歩いていると心も身体も浄化されていくような気持ちのよいものであった。いつもは本殿まで行って引き返すのだが、その日は特別だった。「お父さんが無事に帰って来られるようにお祈りして行こう」と母が言い、私たちは奥社へお参りに行くことにし、長い石階段を上り始めた。いつもはぐずつく妹も、嫌になるほどの長い階段を、文句ひとつ言わずに上っていた。1時間ほどしてやっとたどり着いた小さく古い社殿は、ひっそりと佇んでいた。そこには、私たちの他にも何人かの参拝客がいて、大事そうに、どこかに通じるかのように、お参りしていた。私と母と妹も、父が無事に帰ってこられるように、心から、祈った。私は父が日本の裏側の世界に行っている間、その世界にいる父を、いつも家にいる父よりもずっと強く意識して生活していた。世界で一番遠い世界にいる父が、今ごろどうしているのか、いつも気になっていた。
駐車場に向かって歩いていると途中に清流があった。「わあ、きれい」と母がその清流の美しさに感動していた。私たち3人はその清流をしばらく眺めていた。自然の水草がきらきらしていて、まるで父の石組レイアウトを彷彿させるような、洗練された自然の美しさがそこにはあった。私たちの祈りに、父の何かがそっと呼応していたかのように。もしかしたら、それは母の想いに応えたものかもしれない。誰よりも母のために父に無事に帰って来てほしい、そう思ってしまうほど、私は心配性の母も気になっていたのだ。
数週間後、真っ黒に日焼けして、痩せこけた父が帰って来た。けれども、とても良い顔をしていた。話を聞くよりまずその姿が、父が何を見て、得てきたのかを物語っていた。父は沢山のお土産を私たちに持って帰って来てくれた。見たこともない色合いのタペストリーには動物や植物が手刺繍されていた。ミサンガやヘアバンド、バッグ、そこからは初めての匂いがした。世界の裏側からやって来たものたちを自分の部屋に持って行くと、所在なさそうに、他のものから浮いていた。その夜は、母が父の好きなものばかりをこしらえて、私たちは父の帰還をお祝いした。

父は20年後の今、初めて知るだろう。ほんの一瞬でも、世界の裏側から自分のために小さな祈りが捧げられていたことを。地球からしたらあまりに小さな私たちは、永遠になぞなぞ迷路で迷っている。けれども、誰かがどこかで自分のために、心から強く、祈ってくれる瞬間がある。その真実は、地球がきまぐれで与えてくれる数あるヒントのひとつなのかもしれない。そんな気がする。
2014年 月刊アクア・ジャーナル vol.224掲載「Green Tunnel」より
2014年 月刊アクア・ジャーナル vol.224掲載「Green Tunnel」より